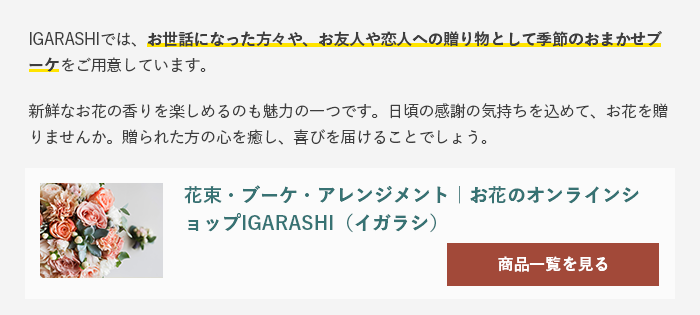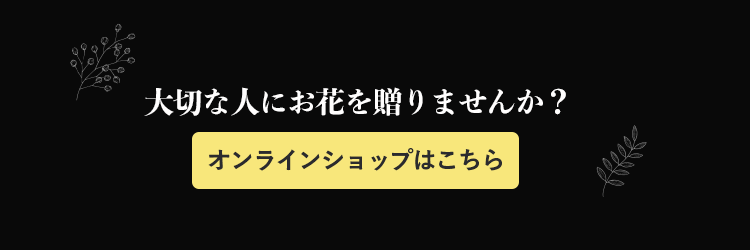【保存版】お供え花のマナー|選び方や種類についても解説
お供え花を贈る際、「どんな花がふさわしいのか」「マナーに合っているのか」と悩んでいませんか?
この記事では、葬儀や法要の場で失礼に当たらないお供え花の選び方や、避けるべき花の種類、贈る際のマナーについて詳しく解説します。
例えば、派手な色合いの花が不適切とされる理由や、贈り先の負担を減らす花の選び方など、実際の場面で役立つ具体的な情報が満載です。
さらに、個人で贈る場合や会社として贈る場合の適切な価格相場も紹介します。
この記事を読むことで、お供え花選びの基本を押さえ、贈り先様や遺族に対して真心が伝わる選び方ができるようになります。
この記事を参考にすれば、誰にとっても失礼のない、心温まるお供え花を贈る方法がわかり、自信を持って行動に移せるでしょう。

この記事の監修者
五十嵐 平
福井県生まれ。日本フラワーカレッジ卒業後、東京、南青山のフラワーショップで修行。現在は株式会社いがらしの代表。
常に贈る人、贈られる人の立場で、その瞬間が一生の思い出となるような感動をあたえられるように、サービス・商品の改善に努めております。
目次
お供え花の意味

供花とは、通夜や葬儀の場で、故人の冥福を祈り、深い悲しみにある遺族を慰めるために贈られる花です。
また、故人への別れの挨拶や、祭壇を美しく飾る役割も担っています。
この習慣は、お釈迦様が入滅された際、枯れかけていた花々が再び咲き誇り、お釈迦様を包み込んだという逸話に由来しています。
現代では、故人やそのご家族と親しい関係にあった方々が供花を贈ったり、葬儀に参列できない方が弔意を示す手段として贈られることがあります。
お供え花のマナー

お供え花のマナーは以下のとおりです。
- カラフルな花はNG
- 避けるべき花の種類
- 花の管理
順番に解説します。
カラフルな花はNG
通夜や葬儀の場では、派手な色合いの花は不適切とされています。
白を基調とした落ち着いた色合いの花を選ぶのが一般的です。必要に応じて、淡いピンクや紫など、控えめな色合いを少し加える程度に留めましょう。
避けるべき花の種類
特定の花はお供えに適していない場合があります。
たとえば、トゲのあるバラや、強い香りを放つ花(カサブランカなど)は避けるのが無難です。
また、椿や彼岸花のように散る様子が不吉とされる花も避けましょう。
花の管理
贈った後も花が長持ちするよう、管理がしやすい種類を選びましょう。
特に、水替えが頻繁に必要な花や散りやすい花は遺族に負担をかける可能性があります。
菊やカーネーションなど、比較的手間がかからない種類がおすすめです。
お供え花の種類

お供え花の種類は以下のとおりです。
- 菊
- カーネーション
- ユリ
- トルコギキョウ
順番に解説します。
菊
供花によく用いられる白菊には、さまざまな意味や理由が込められています。
白菊が選ばれる背景には、花言葉が「ご冥福をお祈りします」を表していること、白という色が清らかさや無垢を象徴すること、さらに花の形状が整っていて長持ちすることが挙げられます。
白菊が供花として広く浸透したのは、19世紀のフランスで万霊節に墓前に飾る習慣が始まったことがきっかけと言われています。
その風習が中国を経て日本にも伝わり、現在のように定着しました。
また、中国や日本では、菊は長寿を象徴する花とされてきました。
江戸時代には、菊酒を飲んだり、菊のエキスを染み込ませた綿で体を拭ったりすることで長寿を願う風習も見られました。
現在、菊は枕花や後飾り花、仏壇の花、手元供養の花、さらには墓参り用の花として広く使われています。
カーネーション
カーネーションといえば、母の日を連想する方が多いでしょう。
母の日には赤いカーネーションを贈るのが一般的ですが、その背景には、白いカーネーションを亡き母に捧げたエピソードが関係しています。
現在でも白いカーネーションは、母の日に亡き母を偲ぶ花として用いられています。
供花としてのカーネーションは、枕花や後飾り花、仏壇の花、手元供養の花、墓参りの花などに広く使われています。
特に暑い夏でも他の花に比べて長持ちすることから、菊に次ぐ人気を誇ります。
ピンクやブルー、ライム色のカーネーションを白い菊やユリと組み合わせることで、上品さが増し、華やかな供花として仕上がります。
ユリ
白いユリは、西洋では純潔の象徴として聖母マリアと関連付けられています。
キリストを授かる場面や、天国の女王として描かれる絵画にも白いユリが登場します。
一方で、日本ではユリは美しいものの例えとして用いられています。
「歩く姿は百合の花」ということわざは、そよ風に揺れるユリの花と美しい女性の歩き方を重ね合わせたものとして知られています。
ユリの仲間は、アジアを中心にヨーロッパから北アメリカの亜熱帯から温帯地域にかけて、100種類以上が自生しているとされています。
そのうち日本では、7種類が確認されています。
トルコギキョウ
トルコギキョウは、北アメリカのコロラド州からテキサス州にかけて自生する2種類の植物です。
日本には、大正時代から昭和時代にかけて伝えられました。
昭和40年代後半には、品種改良が活発に進められるようになります。
これにより、色や形、大きさが多様な品種が次々と誕生しました。
約30年間でおよそ1000品種が生み出され、日本は品種改良の中心地として注目されました。
関連記事:【保存版】タブーなお供え花の種類|お供えに適したお花も紹介
お供え花の選び方

お供え花の選び方は以下のとおりです。
- 場面や宗派に合わせた花選び
- 適切な花の種類
- サイズとボリュームの配慮
- メッセージカードや花札の付け方
- 季節感を取り入れる
順番に解説します。
場面や宗派に合わせた花選び
お供え花を選ぶ際には、場面や宗派に合わせた選択が重要です。
葬儀や告別式の場合、白を基調とした清らかな花が一般的であり、菊やユリ、カーネーションが多く選ばれます。
これらは厳粛な場にふさわしい花として認識されています。
一方、法要やお盆では宗派や地域の慣習によって選べる花の種類が変わりますが、ピンクや紫のように落ち着いた色合いの花が許容される場合もあります。
お彼岸や命日では、季節の花を取り入れることで、自然の美しさと故人を偲ぶ気持ちを一緒に伝えることができます。
適切な花の種類
お供え花には、仏花として定番の種類があります。
菊、ユリ、カーネーション、アイリス、蘭などは、その清楚さと意味合いから選ばれることが多い花です。
ただし、注意すべき点として、棘のあるバラや毒性のある植物、または派手すぎる色合いの花は避けるのが一般的です。
これらは不適切とされる場合があるため、贈る際には慎重な選択が求められます。
サイズとボリュームの配慮
お供え花を選ぶ際には、サイズやボリュームにも注意が必要です。
仏壇や祭壇に置く場合、限られたスペースを考慮して、適切なサイズの花束やアレンジメントを選びましょう。
また、手間のかからない形式であるフラワーアレンジメントは、贈り先にとっても扱いやすく好まれる選択肢です。
過剰に大きな花束や扱いが難しいデザインは避けるのが無難です。
メッセージカードや花札の付け方
お供え花には、メッセージカードや花札を添えることが一般的です。
これにより、送り主の名前や故人への想いを伝えることができます。簡潔で丁寧な言葉を用いて、故人やご遺族への敬意を示すことが重要です。
特に形式を重んじる場では、適切な書式で記載するよう心掛けましょう。
季節感を取り入れる
お供え花には季節感を取り入れることも大切です。
春には桜やチューリップ、夏にはアサガオやヒマワリ、秋にはコスモスやダリア、冬にはポインセチアやシクラメンなど、四季折々の花を選ぶことで、自然の美しさを通じて故人への思いを伝えることができます。
季節感のある花を贈ることで、贈り物に温かみを加えることができます。
お供え花の相場
贈り先様との関係性にもよりますが、一般的にお供え花の価格帯は、個人で贈る場合は5,000円から10,000円程度、会社や複数人で連名の場合は7,000円から15,000円程度が目安とされています。
まとめ
お供え花は、故人の冥福を祈り、遺族を慰める大切な贈り物です。
そのため、選び方や贈る際のマナーには細心の注意を払う必要があります。
まず、通夜や葬儀では、白を基調とした清楚な花を選びましょう。菊やユリ、カーネーションは定番で、宗派や地域の慣習によっては淡いピンクや紫を加えることも可能です。
一方、バラのような棘のある花、散る様子が不吉とされる椿や彼岸花、香りの強い花は避けるのが無難です。
最後に、贈る花の価格帯は、個人の場合は5,000円~10,000円、連名では7,000円~15,000円が一般的な相場です。関係性に応じた適切な選択を心がけましょう。
「相手に喜ばれる素敵な花をプレゼントしたい」
「心から喜ばれる花の選び方がわからない」
「気持ちを込めて花を贈りたい」
などとお考えではありませんか?
お花の種類は多くて何を選んだらいいかわかりませんよね。
フラワー&フルーツいがらしでは、お花を1つひとつ丁寧にお作りし、丁寧にお届けします。
人と人との心を繋ぎ、コミュニティを深めることで人や地域が 明るく豊かになる、お手伝いをしています。
お花の注文・相談については以下からお願いします。